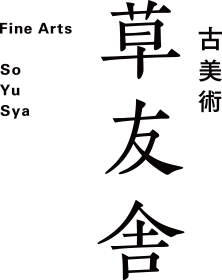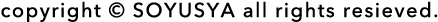2026.1/7
仏像カレンダー
年が明けて七日、
今年も草友舎のホームページやインスタグラムをご覧いただいたり、お店や催事などでお会いできましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
*
年末の拝観の記録
2017年に奈良国立博物館で開催された「源信」展で、その時も感激したとは思うのだが、奈良仏像カレンダー2025であらためて見て以来、拝観目標にしていた観音像を年末に訪ねることができた。
そこは寺跡で住職がおられないので、問い合わせは事前に電話で近所のお寺に申し込む。
最寄駅は近鉄南大阪線にあり、そこから20分ほど歩くが、JRを使っての最寄駅から徒歩40数分の行き方を選んだ。
奈良駅ではそうでもなかったのに、一回乗り換え計8駅目で下車すると、薄曇りでかなり気温が低いうえに山から降ろす風が冷たくて強い。
麓にあるお寺を目指して、風に向かって前のめりになりながら刈り取られた田圃や畑の間の道を歩く。
昔と現代とでは大変さが比較にならないが、こういう苦労をしていると、自分が古い縁起絵巻の添景に描かれた行脚する人物になったような気分になってきて嬉しくなる。
30分ほど歩くと少し上り坂になり、古い民家や木々の間の細い道を進み、約束の時間に目的地に着いた。
小さな礎石が遺っている三間四方くらいの空き地のすぐ横に古びた収蔵庫があり、電話で応対してくれた住職の奥さんが、収蔵庫の扉を開錠してくれた。
1メートルと小ぶりだが、いかにも10世紀らしい量感のある観音像と、12世紀の薬師如来像、役行者像、鎌倉時代はあるであろう獅子と狛犬、奉納絵馬などが小さな室内に並んでいる。
観音像はカレンダーの写真で記憶は新しくしていたが、実際に見ると、子熊のぬいぐるみのような可愛らしさも持ち合わせているように感じて親しみが増した。
冷えた両手をさすりながら奥さんはいろいろ教えてくださった。
この像は観音堂に安置されていたが、昭和43年にすぐ横に建てられた収蔵庫に移された。
その後、観音堂は火災に遭う。
その日は風がなく、火柱が真っ直ぐ上にあがっていた、と奥さんは話して、また思い返したようにもう一度繰り返した。
もしも収蔵庫に移されていなかったら、と思うと、兼ねてから収蔵庫での拝観は少し味気ないと思っていた考えをあらためなくてはならないような出来事だ。
収蔵庫の維持費など、大変なのだそうだ。
写真も撮ってよいと言ってもらったので、撮った写真をSNSなどに投稿してもよいかと尋ねると、ぜひそうしてほしいとのことだった。
芳名帳の最後の記入は9月⚪︎日、
仏像、狛犬、お供え、奉納絵馬などたくさん写す。
この集落の信仰心にもふれられたような温かな心持ちになって、今年はこのひとつのお寺を訪ねただけで充分に満足した。
ようやく麓に近づく





在りし日の観音堂の写真と瓦